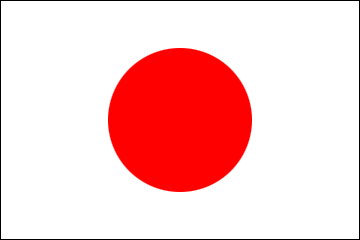特定非営利活動法人 カラ=西アフリカ農村自立協力会

特定非営利活動法人 カラ=西アフリカ農村自立協力会
村上一枝 代表
1) 協会の紹介
当会は、特定非営利活動法人の「「カラ=西アフリカ農村自立協力会」と言い、1993年に設立されました。マリ共和国において農村部に住む人たちが自立に向けて努力する事を支援する団体です。
その為に、日本から資材を持ち込まず、全て現地で得た資材を使い、現地の技術と力によって「生きる」事に必要な基本的事項を複合的に重ね合わせて事業を進めています。スタッフは、すべてマリ人技術者と村に住む青年男女を中心とし、将来を担う人材の育成を兼ねています。
当会の主な事業内容は、(1)水資源の確保、(2)保健衛生知識普及と病気予防、(3)教育の普及、(4)女性の生活改善、(5)環境保全等です。
2) マリで働いて一番大変だったこと
意識の違いです。支援を必要とする国の環境を考えると、その他の多くは大変な事とは言えません。
3) 現在の活動分野に携わるようになった経緯・きっかけと事業の説明
1960年代から始まった気候変動によるアフリカを襲った干ばつで、人々の日常生活の危機が大きく報道され、目を覆うような状況でした。このような時には緊急支援も重要ですが、恒久的に人々の日常生活に活かされる支援も重要であると思います。たとえ干ばつの被害を受けても、人々の知恵で最小限の生活は可能になるであろうという考えで、1989年10月、アフリカでの支援を始めました。スタートとして、将来を担う子供達の健康についての支援を考え、1989年10月からサハラ砂漠のティンアイシャ村に滞在しました。村では、病気の子供や長年の怪我を負ったままの人、また結核の人がいても、食べる事も満たされず、診療所もない村では病を癒す手段がありません。静かに死を待つのみが現状でした。日本で考えていた医療分野への支援はかなり困難で、そこに至るまでの経過が重要であると改めて知りました。このような状況はサハラ砂漠だけではありません。現在でもマリの多くの村には診療所、薬局もドクターもいないのです。たとえ薬があっても、金が無く購入する手段もないのが現実です。支援する側が地域の開発や自立を唱えても、中心になる人間は、健康な日常生活を送り、物事を知り考える手段が与えられなくてはいけません。それらを考えた結果、当会の支援の目的は、人々が【生きる】為に必要な基本的手段を得る事への支援となりました。
このようにして教育、農業、林業、医療、その他の必要な事項を支援事業の課題に取り上げ、しかも村人の意識や、潜在的な能力、そして自主性に合わせて事業を進めていきました。
村に不足する水の供給をスタートとして、人々と共に事業を進めた結果、女性が収入を得るようになり家庭内暴力も減少しました。未熟児の誕生がゼロに、女性は文字を学び識字教室でも女性数が男性数を大きく上回っています。教育への理解が深まり就学児童が増加し、中学校に進学する生徒も出て、過去に小学校を建設した村には中学校が開校しました。母親たちが組織する健康普及員の必死な働きにより下痢の子どもが30%減、感染症も減りました。男性も家族計画を理解するようになりました。女性が蓄えた資金で貸付事業を2002年に開設し、現在まで継続しており、出稼ぎ少女が90%減少しました。村から誕生した助産師は少女達に新しい女性の生き方を示しています。殆どの事業は村人が管理出来るようになり当会は手を離しました。伝統的に男性優位の社会ではありますが、この成果は真摯に働く女性の姿と、それを理解する男性にあると考えています。
しかし保健部門での人材育成、学校建設が大きな問題として残り、現在は双方の事業が主体となっています。
2015年度、外務省の日本NGO連携事業によって、教育施設が非常に貧困である地域に小学校1校と中学校1校が建設されましたが、これは、義務教育充実の一環を担うものです。雨季には資材の輸送は困難の為、雨季前に現場に運び込み、現8月はクリコロ圏ドゥンバ郡ニャマコロブグー小学校、同郡のシンザニ中学校の建設はほぼ終了に近くなっています。2015年12月に開校式を行なう予定です。
ニャマコロブグー小学校へは近郊5ケ村から子供が集まり、雨季の強風や豪雨を避けて安全な教室での授業が確実になります。シンザニ中学校は、地域約21ケ村内に2番目に開設された中学校です。まだこの地域には高等学校はありませんが、確実に学校建設が進むと義務教育修了者が増え地域の発展に繋がります。
4) 仕事のやりがいを感じるとき
指導したことが、時間を経て確実に成果として実ってきたこと。
5) 今後の目標
ますは、義務教育修了者を増加させることです。それから、家族の健康は母親が護ることを目的に、女性保健普及員を育成し非常に高い成果を上げているので、2016年から他地域で同様の事業を実施したいと考えています。獣医の育成も目標の一つです。
6) 日本の方へのメッセージ
- 現在、世界的に問題となっている「イスラム国」について、本来のイスラム教徒は彼らとは全く違います。真のイスラム教徒の姿を知って欲しいと思います。
- 発展途上国への支援は、我々の日常生活上のことと理解して、家庭で子供と両親が話題とするようになることを希望します。これは親の教育分野でもあると思います。
- 子供や学生たちが、事件性だけを追わないで、また、その国の発展状況にかかわらず世界の国々の人の生活状況を日常的に目に出来るよう、報道番組を制作し放映する事を希望します。
- 外務省で、毎週2回くらいは世界の国の情報を流して下さい。
写真

診療所開設について保健担当員への学習会
(2011年度、外務省日本NGO連携事業:クリコロ圏スウバ郡スウバ村診療所にて)

2014年度NGO連事業
建設がほぼ終了したシンザニ中学校